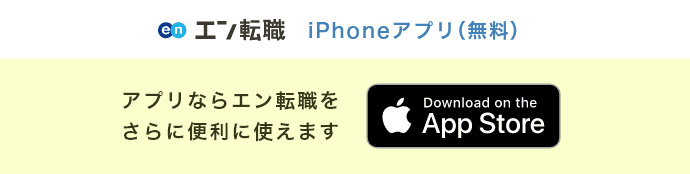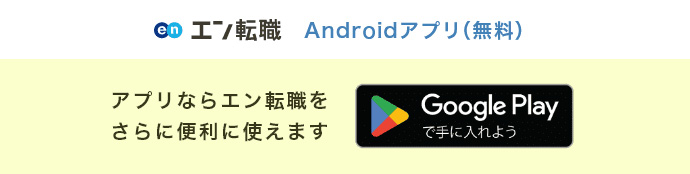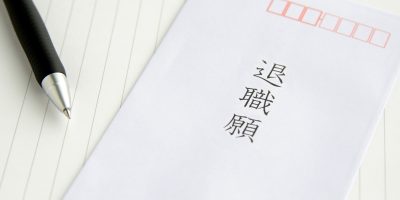試用期間って何?退職もできる?|試用期間の意味、試用期間中の納得されやすい退職理由をご紹介!

仕事探しの際、求人情報をチェックしていると記載されている試用期間という言葉。これって一体何を指しているのか、ご存知ですか?よく知らないまま読み飛ばしていた、研修期間みたいなものだと思っていた、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、試用期間について詳しく解説します。そもそも試用期間とは何か?どのくらい設けられるものなのか?試用期間中の給与や福利厚生はどうなるのか?そして、退職することはできるのか?などをご説明させていただきます。退職理由例もご紹介していますので、ぜひチェックしてくださいね。
目次
1.試用期間について
試用期間って何?
試用期間とは、簡単に言うと、本採用を前提としたお試し期間のようなものです。数回の採用面接だけで組織にマッチする人材かどうかを見極めるのは難しいですよね。そのため、企業が求職者を採用することになったとき、長期雇用を前提としてその人の勤務態度・能力・スキルなどを見て、本採用するかどうかを決定するために設けられている期間なのです。試用期間を導入するかどうかの判断は企業によって異なるほか、法的に設置が義務付けられているものではないため、通常と同じ雇用契約になります。期間の長さについては、1~6ヶ月が一般的。最長1年が限度と考えられています。なお、試用期間を設ける場合は、就業規則、労働契約書に明記されていなくてはいけないので、きちんと確認することをおすすめします。
試用期間って解雇されやすいの?
試用期間だからといって、簡単に解雇にはなりません。そもそも長期雇用が前提なので、正当な理由(経歴詐称・出勤率不良・勤務態度に問題あり、など)がなければ解雇されないのです。「なんとなく社風に合わない」「期待していたほどの能力ではなかった」といったものは、もちろん正当な理由にはなりません。
また、通知に関しても、通常の解雇と同様で30日前に予告するか、予告の代わりに30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払うかのいずれかが義務付けられています。ただし、試用期間の開始から14日以内は、これらが必要ではないという特例が認められています。前述のとおり、長期雇用を前提として採用されているので、試用期間があるからといって、むやみに不安に思う必要はありません。組織の一員として、適切な行動を心がければ大丈夫です。
試用期間中の給料や福利厚生って?
企業によっては、試用期間中の給与が試用期間終了後より少ない額を提示される場合があります。そのときに気をつけたいのが、各都道府県の最低賃金を下回っていないかということ。気になる場合は、給与額と試用期間の日数を用いて平均賃金を算出(※1)し、最低賃金と比較するようにしましょう。また、試用期間中とはいえ長期雇用を前提として採用している以上、特例(※2)を除き各種社会保険(雇用・健康・労災・厚生年金)への加入が義務付けられています。不確かな場合は、きちんと確認をとるようにしましょう。
(※1)試用期間中の給与額÷試用期間中の勤務時間=試用期間中の平均賃金
(※2)以下の場合は労災保険を除き、適用除外となります。
・2ヶ月以内の期間を定められた臨時雇用者
・日々雇い入れられ、期間が1ヶ月以内の者
・4ヶ月以内の季節労働者
・6ヶ月以内の臨時的事業の事業所に使用される者
・所在地の一定しない事業に使用される者
・船員保険の被保険者
・国保組合の事業所に使用される者
2 試用期間中に退職したいと思ったら?
試用期間中の退職における注意点
「実際に働いてみたらイメージと違った…」「組織の雰囲気と合わない」「仕事のことを考えると憂鬱で体調が優れない」などの理由で試用期間中にやむをえず退職…。これはありえない話ではありません。では、退職しようと思ったらどうすればいいのでしょうか?
注意しなければならないのは、即日退職は原則NGであるということ。正式採用ではない試用期間中だからといって、辞めたいその日に退職を申し出たり、即日退職したりということはできません。試用期間中であっても労働契約は成立しているため、会社のルールを守った上で退職する必要があります。労働基準法では、退職予定日の2週間前に退職の申し出を行なうことが定められていますが、「退職を申し出る場合は退職希望日の1ヶ月前までに申し出ること」などの規定があれば、それに従わなければいけません。
「自己都合の退職であること」「明確な退職の意思があること」を意識し、退職を決意したらできるだけ早く申し出てください。
試用期間中の退職手順
試用期間中の退職には「自主退職」と「合意退職」があります。試用期間中に辞める・退職する際は、会社がどちらの退職に区分するかによって、手続きなどが違ってくるのです。
■自主退職の場合…
労働者の一方的な意思表示により退職の効力が発生。使用者の同意や承諾は必要ありません。退職届が使用者のもとに届き、一定期間が経過したのちに退職できることになります。この場合、退職届を撤回することはできません。
■合意退職の場合…
退職届の提出によって合意解約を申込み、使用者が受理すると退職の効力が生じるカタチです。使用者の受理前であれば、退職届の撤回もできます。
いずれにせよ、すぐに辞められるわけではないので、退職を決めたらできる限り早めに直属の上司へ伝えるようにしましょう。事前に「ご相談があります」といったカタチでアポイントをとり、上司の時間を確保してください。退職に関することは直接言いづらいかもしれませんが、意志の固さを伝えるためにも電話やメールではなく、直接伝えます。
また、のちのトラブルを避けるためにも、退職届を提出。しっかり書面で残しましょう。企業側からの同意が得られたら、具体的な退職日を相談。引き継ぎに必要な時間や業務状況などを踏まえて相談し、日にちを決定します。退職日までに雇用保険・社会保険などの状況を確認のうえ、手続きを進めましょう。企業から指示される場合は、それに従ってください。あとは引き継ぎをしっかり行ない、最後まで責任をもって仕事を終えてくださいね。
3 .試用期間中の退職理由具体例
退職理由「社風や雰囲気が合わない」
社風や雰囲気は、入社前に把握しておくのが難しいところであり、実際にその環境で仕事をしてみなければわからないことはたくさんあります。時間が経てば徐々に環境に馴染めるかもしれませんが、あまりにも違和感があるのであれば、このように退職の意向を伝えるのもひとつの道です。環境に合わないが、上司に退職したいと言い出せないといった場合、ストレスを溜め込み、カラダを壊してしまう恐れもあります。ぜひ、じっくり考えて答えを出していただければと思います。
退職理由「求めていた環境や仕事ではなかった」
仕事内容は、入社前に採用担当者や現場の方々にしっかり確認していても、入ってみると何かが違うといった違和感を持つことがあるかもしれません。これは、結構多くの方が感じることのようです。自分から周囲へ働きかけるなど、何らかの解決方法がないか、まずは状況を変える努力をしてみるのも大切かと思います。しかし、想像していたものと現実の仕事内容があまりにも異なり、そのギャップの解消も難しい、退職したい、という場合は、こちらもストレート過ぎる理由は伝えず、その仕事をしている人たちを立てつつ、意思を伝えるほうがいいでしょう。
あわせて読みたい
退職届・退職願の書き方ガイド ~違い・テンプレート・封筒の書き方など~
退職願・退職届の書き方ガイドでは、言葉の違いを説明するとともに、書き方や会社への渡し方などをご紹介します。