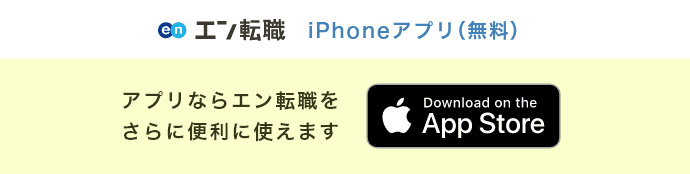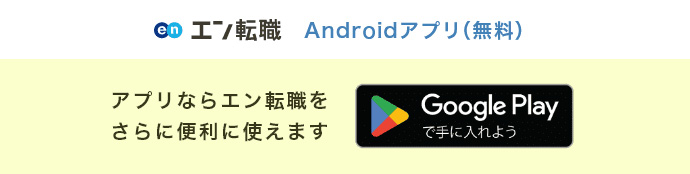転職の最適なタイミングは?転職目的・年齢別にご紹介します。

「友人が転職をしてイキイキとしている」「同年代の友人が結婚・出産した」「自分に合った仕事は他にあるんじゃないか」「今の仕事はやり遂げてしまった」…そんな自身の将来についてふと考えるタイミングは数多くあると思います。そんなとき、「転職」というキーワードが頭をちらつくのではないでしょうか。でも、「いま転職するのがベストタイミングなのか」「今すぐじゃなければいつがいいのか」といった疑問が浮かぶ。転職はそう何回も経験することではありませんから、仕方がないことです。今回の記事では、転職のタイミングにまつわる疑問に、「転職目的」「年齢」ごとにお答えします。あなたにとっての“転職のベストタイミング”を見極める参考にしてみてください。
目次
1.転職目的ごとの転職タイミング
同業界でのキャリアアップを目指す転職のタイミング
「今の会社ではキャリアに限界がきた」「仕事をやりきった」と感じたときが、キャリアアップを目指す転職に向けて動き出すベストタイミングと言えます。採用企業が面接時などで気になるのは、入社者が前職で「どんな経験を積み、どのようなスキル・知識を持っているのか」ということ。あなたが「目指すキャリア」や「その実現のために取り組んできたこと」「転職後に身に付けたチカラをどう発揮してくれるのか」を具体的に知りたいと考えています。「現職では自分の理想とするキャリアに限界を感じ、その続きを次の会社で歩みたい」という転職ですから、採用企業も好意的に受け止めてくれるでしょう。
逆の捉え方をすると、キャリア形成や仕事が中途半端の状態では、まだ転職のタイミングではないと言えるでしょう。大切なのは「今の会社ではやりきった」と、エピソードを交えて語れるかどうか。もしも、あなたがキャリアアップを目的とする転職を目指しているとしたら、「自分はどんなキャリア形成をしたいか」「そのためにやったことは何か」をいま一度振り返ってみることをお勧めします。「まだまだ今の会社でやれることがあるな」と感じたら、それを成し遂げてからでも、ぜんぜん遅い転職のタイミングではありませんよ。
他業界へのキャリアチェンジを目指す転職のタイミング
他業界へのキャリアチェンジを目指すタイミングは、一般的に「30歳まで」がベストのタイミングと言われています。今まで経験してこなかった「業界・企業の文化・商習慣・風土などの環境」に、転職者があまりストレスを感じず適応しやすい、と考えられている年齢の目安が30歳までなのです。
たとえ前職で5年のキャリアがあったとしても、転職先では未経験からのスタート。その業界・会社での仕事を、企業は入社後に教えていくことになります。前職での勤務期間が長いと、その環境や仕事の進め方が身体に染み付いている場合が多く、企業も教育に時間を費やすことに。だから、環境に柔軟に馴染みやすい、という観点で、多くの企業がキャリアチェンジを受け入れる年齢の基準を設けています。
転職者の中には、「社会人経験の浅いうちから他業界へのキャリアチェンジは不安がある…」と考える方もいらっしゃるかもしれません。でも、過度な不安を感じる必要はないです。業界が変わっても、ビジネスパーソンとしてのスキルや心構えは通用するものが大半です。 “入社後に学ぶべきこと”“入社後に活かせること”を整理し、活かせることは採用企業に自信を持ってアピールしてください。
資格を活かす転職のタイミング
資格を取ってからのタイミングで転職活動をするほうが、有利になる。これは、半分正解で半分不正解と言えるでしょう。やみくもに資格を取得しても、効力を発揮しないこともあるからです。やはり企業は、募集職種に対応した資格を持つ方に魅力を感じます。例えば…。
◎経理募集 ⇒ 日商簿記
◎海外営業 ⇒ TOEIC
◎不動産営業 ⇒ 宅地建物取引主任者(宅建)
◎貿易事務 ⇒ 通関士
◎秘書 ⇒ 秘書検定
など、実務に紐付く資格が評価の対象になることが多いようです。極端な話ですが、経理募集なのに「日商簿記」ではなく「通関士」の資格だけが履歴書に書かれていたら、採用担当は「経理ではなく、貿易事務に転職したほうがいいのでは?(転職するべき企業は当社ではないのでは?)」と感じてしまうでしょう。資格を強みに転職をするなら、採用企業の実務につながる資格を取得してからが、そのタイミングとなるのです。
ただひとつ注意するべきは、資格さえあれば転職は万事OK!…とはならないこと。仕事をする上で、求められる“実務スキル”というのがあるものです。コミュニケーション能力や仕事をやり切るチカラなど、採用企業が求めるスキルをアピールすることが先。それができれば、資格が有利に働くでしょう。
結婚・育児などのライフイベントに合わせた転職のタイミング
<女性のタイミング>
結婚・育児と仕事の両立ができる職場。もしも今の会社がそういう環境でなければ、転職という選択肢が挙がるでしょう。では、いつ転職するのがベストなのか。産前産後休暇・育児休暇の取得に関する法令から、そのタイミングが分かります。
まず産前産後休暇については労働基準法で定められ、「出産前6週間は妊婦からの申請があった場合に、会社は必ず付与しなければならない」とされています。出産後8週間は、本人の申し出の有無に関わらず産後休暇が付与されます。
一方で、育児休暇について定められている育児介護休業法では「入社から1年未満の従業員に対しては、労使協定の書面に基づき拒否することができる」という旨の内容が書かれています。
まずは育児休暇に関する労使協定の内容を入社前に確認することがひとつの手。でも、なかなか聞きづらいと思います。となると、育児休暇を取得することを見据えて、【出産を考えている時期から1年以上前】が転職のタイミングと言えそうです。転職活動を始める前に、パートナーと家族の人生設計を話し合ってみてはいかがでしょうか。
<男性のタイミング>
男性にとっても、結婚・育児といったライフイベントは転職を考えるタイミングです。「“夜勤の仕事をしている”“残業が多い”という働き方だから、家族との時間をとれる職場に転職したい」「子どもが産まれたときのことを考えると、今よりも高い給与を目指せる会社で働きたい」などの理由で転職をする方もいらっしゃいます。
男性の場合も、ベストなタイミングを見極めるために、パートナーとの相談から始めることをお勧めします。例えば、転職先では初任給が下がるリスクもあります。残業が短くなっても、お子さんが産まれるまでに家計を支えられる給与にアップしていなければ、収入の問題がチラつくことに。【出産予定時期の1年以上前】から、計画的に転職のタイミングを検討するのがベストと言えそうです。
新卒入社の会社をすぐに退職したいときの転職のタイミング
一般的には、「新卒で入社した会社には最低でも3年は勤めたほうがいい」とされています。この話が世間をひとり歩きしていますが、では、そう言われる理由は何のでしょうか?
理由1)基本的なビジネススキルが未成熟
社会人経験が3年以内ですから、まだ働いた経験そのものが短い。先輩に比べれば、まだまだ駆け出しでもできる仕事を任されていることが多いでしょう。つまり、経験不足なので、ビジネススキルが未成熟(仕方のないことですが…)。中途採用をする企業にとっては、新卒採用ではないので、ビジネスマナーのイロハから教えることは避けたいものです。
理由2)ガマンができないと思われる
学校と会社は、全く別のもの。当然、学生のときには経験してこなかったことの連続で、仕事の失敗もたくさんしている時期が入社3年以内でしょう。そこを乗り越えるまで粘り強く取り組めない、つまりガマンができない人と企業に見られる可能性が高いです。企業にとっては「当社に入社してもすぐに辞めてしまうのでは…」と不安になってしまうのです。
以上のような理由から、「新卒入社から3年は働くべき」と言われています。もしも、ビジネススキルやガマン強さに自信があり、企業にアピールできるものがあるなら、3年を待たずしても転職のタイミングとなるでしょう。「まだまだ自信がないな」という方は、せっかく縁があって入社した今の会社で学ぶことをお勧めします。
2 .年齢別の転職タイミングと採用企業から求められること
25歳のタイミングでの転職
25歳は先ほど触れた「新卒入社から3年間の勤務」を経過する頃です。最近の転職市場では、20代の若手を採用する意欲の高い企業も多数。同業界・異業界を問わず、転職しやすいタイミングです。
では、企業はどのようなタイプの人材を求めるのでしょうか。25歳は社会人としてはまだ経験が浅いため、企業は“ポテンシャル採用”という位置づけで採用活動を実施。即戦力ではなく、将来の活躍を期待しています。具体的に求めることは、前項目で挙げた「基本的なビジネススキル」「ガマン強さ」といったあたりがベースです。これらから発展して、「先の仕事を想定して、自ら動ける、上司・先輩に質問できる」「仕事を作業ではなく、目的を持って取り組める」などの“仕事・成長への意欲”に期待する傾向があります。
これまでのキャリアを継続するのもアリ。新しいキャリアにチャレンジするのもOK。可能性に満ちた転職のタイミングですから、あなたが目指したいキャリアを見つめ直す、いい機会とも言えるでしょう。
30~34歳のタイミングでの転職
30代前半の転職は、20代までとは違い、即戦力性が求められる傾向にあります。多くの採用企業は、入社後すぐにプレイヤーとして活躍してくれる人材を採用したい、というスタンスです。20代が中心となるスタートアップ企業では、若手を牽引する役割が期待されることもあるでしょう。一定のパフォーマンスが求められるので、「前職での実績」と「どんなスキルを身に付けたか」という点が、転職において重要になってくるタイミングなのです。
30代前半になったときに転職という選択肢を持つためにも、20代の頃から実績を作ることを意識することをお勧めします。もしも「実績なんてないな…」とお悩みの方も、自身が仕事でやってきたことを棚卸ししてみてください。大きな成果はなくても、ビジネスパーソンとしての今のあなたをカタチ作った成果がきっとあるはずです。「それでも見つからない」という場合は、自信を持って語れる実績を作ってからでも、転職のタイミングとしては遅くありません。
35~39歳のタイミングでの転職
35歳を過ぎると、ほとんどの企業が「管理職」または「管理職候補」としてあなたを見ます。プレイヤーとしてのスキルに加えて、転職においてマネジメント力が大切になってくるタイミングなのです。
マネジメント力と言っても、「マネージャー」などの肩書きを持っていなければならない、というわけではありません。「社内で進行しているプロジェクトの取りまとめ役」や「後輩の教育担当」などの経験を評価する企業も数多くあります。そういった経験を通じて、「メンバーをまとめるために工夫したこと」「仕事を教えるコツ」といったノウハウを身につけていることが重要。採用企業はその話を聞いて、入社後のそう遠くない将来にマネジメントのポジションで活躍している、あなたをイメージするのです。
もちろん、マネージャーなどのポジションに就いている場合はアピールしてください。この場合も、マネジメント業務を通じて蓄積したノウハウはアピールするべき内容です。そのスキルが自社でも活かされるか、採用企業は注目しています。
35歳以降の転職は求められるスキルレベルが上がるため、決して簡単ではありません。自分に合う求人を見つけたタイミングで具体的な行動を起こし、機会を逃さないようにしてくださいね。
3 . 転職活動の準備をするタイミング
今すぐ転職をしない“転職予備軍のタイミング”でやっておく準備とは?

上記の図のような流れで、転職活動が進みます。では、いつ・どのような準備をすればいいのでしょうか。まず、今すぐ転職をしない“転職予備軍”の方は【STEP1 事前準備】【STEP2 情報収集】を行なっておくといいでしょう。
【STEP1 事前準備】
事前準備とは、あなた自身についての整理です。具体的には「キャリアの棚卸し」「何を求めて転職するか」という大きく2点が挙げられます。
まず「キャリアの棚卸し」では、前職で手掛けてきた仕事を整理し、「どんな実績を挙げたか」「どんなスキルを身に付けたか」などを抽出。応募書類や面接でアピールする自身の強みを見つけます。すぐに自己PRができる状態を作っておくことで、転職活動を開始したときに具体的なアクションに移りやすいです。
次に「何を求めて転職するか」について。「キャリアアップ」「労務環境の改善」「収入アップ」など、何でも構いません。「転職活動を始めたいけども、どんな企業に応募すればいいか分からない…」という状態を避けるためにも、自分の中で転職先を選ぶ軸を持っていることが大切です。
【STEP2 情報収集】
こちらは、具体的に企業の募集について調べてみるステップです。転職サイトに掲載されている求人情報に目を通しておくことで、「給与相場」「その業界での仕事」などの相場感を掴めるようになります。転職活動を本格的に始めたときに、応募先を選ぶひとつの基準となるので、まずは気楽にチェックしてみることをお勧めします。
本格的に転職活動を始めたタイミングにやることは?
転職活動を始めたら、【STEP3 求人に応募・応募書類作成】【STEP4 面接】【STEP5 内定・退職手続き】のステップに進みます。
【STEP3 求人に応募・応募書類作成】
特に在職中となると、転職活動に多くの時間を割くことが難しくなります。応募先企業を厳選し、応募書類を作る時間は可能な限り短縮したい。そう思うのが一般的です。そこに、STEP1やSTEP2の準備が効果を発揮します。転職先を選ぶ軸を決めていますし、自己PRもイメージができているため、悩む時間は必要ありません。自分が決めた方向性で転職に向けて動き出しましょう。
【STEP4 面接】
面接に関しても、既にキャリアの棚卸しをSTEP1で完了済み。自己PRは自信を持ってください。また、企業研究でもSTEP2の情報収集が活きてきます。何社かの求人情報を見たことで、応募先の企業の特徴もイメージしやすくなっているでしょう。
【STEP5 内定・退職手続き】
内定をもらった後は、退職の手続きが始まります。もしも内定をもらったときに進行中のプロジェクトがあれば、転職先や在職している企業との調整で手間取ることに。進行中の仕事がある場合は、それが終わったタイミングで転職活動を始めるといいでしょう。